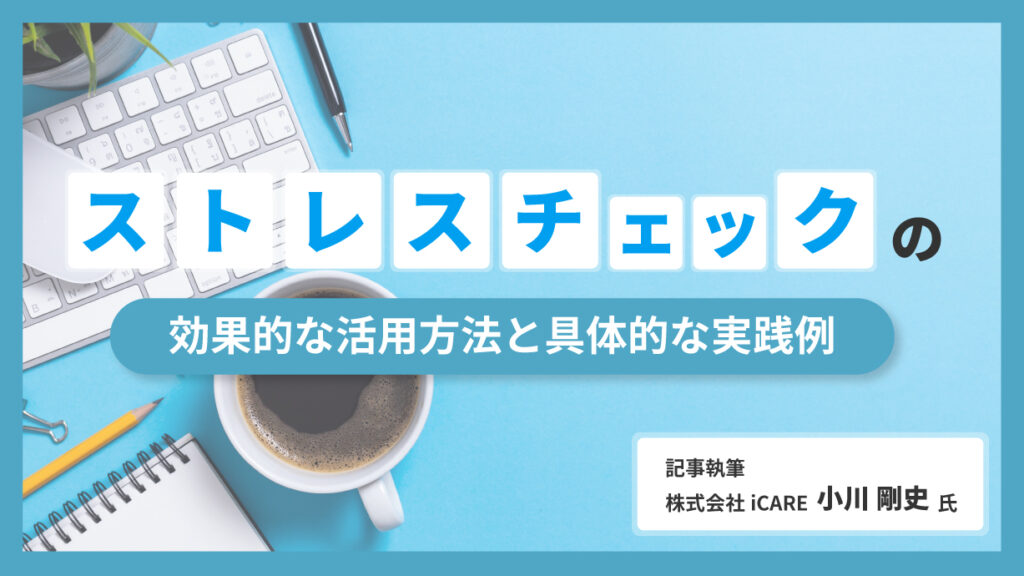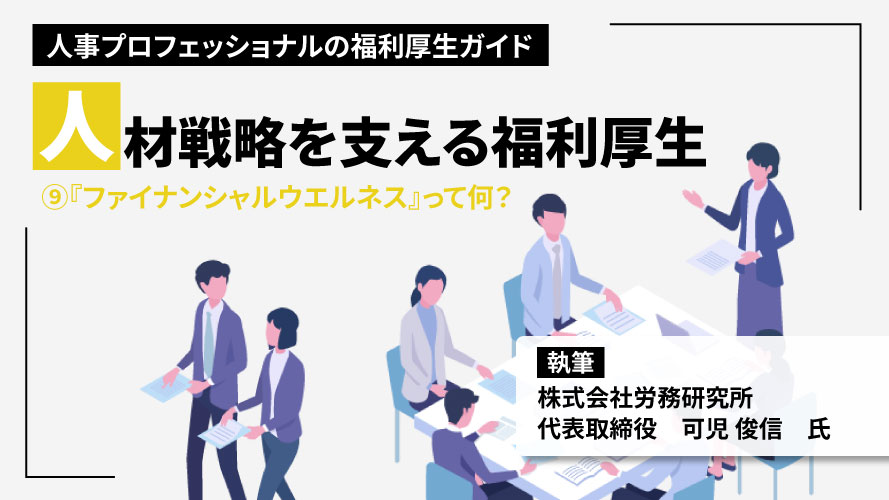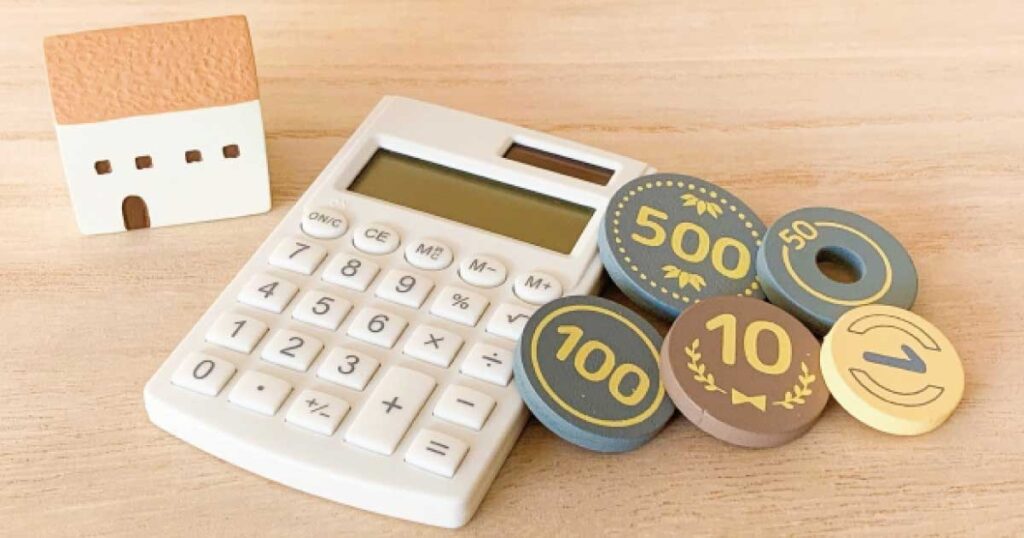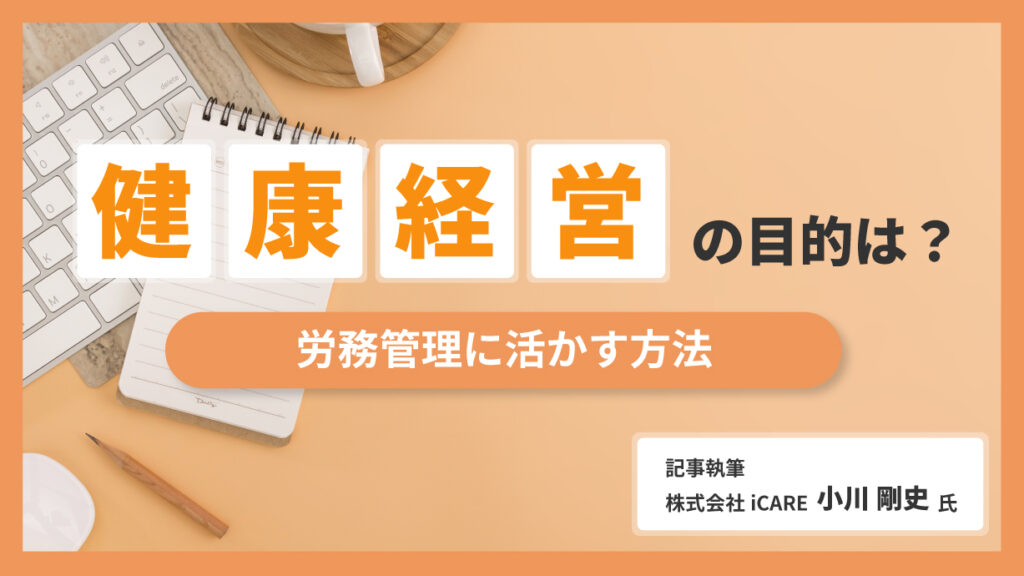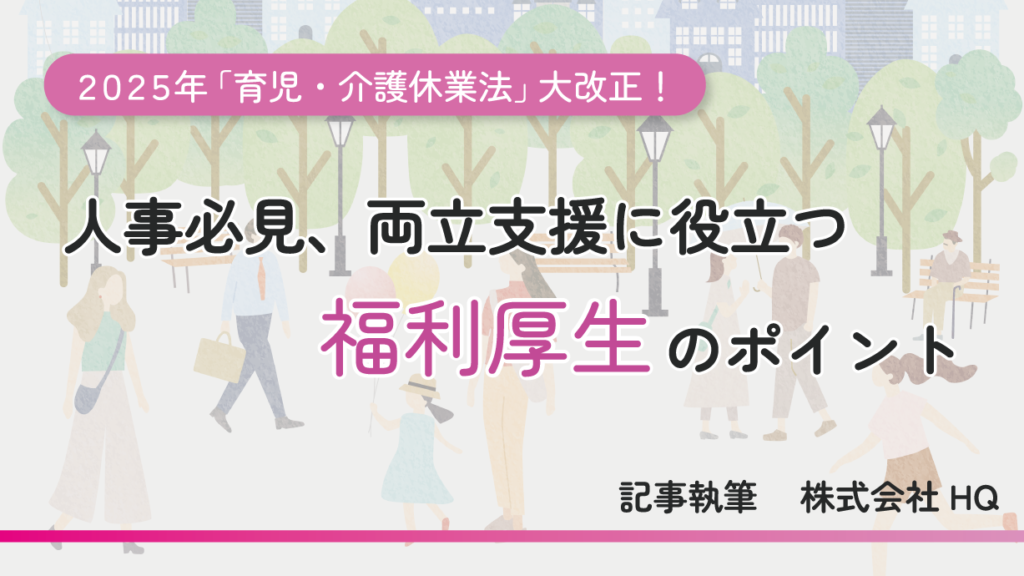新着記事一覧
-

厚労省が長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表
厚生労働省は先日、令和5年度に実施された長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の結果を公表しました。違反内容や指導状況、是正のための企業の自主的な取り組みなど記載されています。 監督指導の概要 監督指導は、1か月当たりの時間外・休日労働... -

慶弔見舞金は割増賃金や社会保険料・労働保険料の対象になりますか?
Q:当社では、従業員が結婚や出産、死亡した場合などに、社内規定に基づいて従業員に慶弔見舞金を支給しています。先月、従業員が結婚をしたので慶弔見舞金を支給しましたが、これは割増賃金や社会保険料・労働保険料の対象になるのでしょうか? A:慶弔見... -

従業員数100人を超える企業に男女間賃金差異の公表義務拡大へ
近年、職場における女性の活躍推進とハラスメント防止は、企業の重要な課題となっています。今回、厚生労働省の「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」が公表した報告書では、これらの課題に関する新たな方向性が示されました。本記事では、企... -

ストレスチェックの効果的な活用方法と具体的な実践例
2015年12月、労働安全衛生法の改正によりストレスチェック制度が開始されました。こころの健康診断とも呼ばれるストレスチェック制度がはじまった背景には、仕事によるストレスが原因で精神障害を発症し労災認定される労働者の増加や、約6割の労働者が強い... -

人材戦略を支える福利厚生⑨「ファイナンシャルウエルネスって何?」
「人事プロフェッショナルの福利厚生ガイド」の第9回です。福利厚生を、人材戦略を支える施策と位置づけ、経営の視点から福利厚生を見直し活用しようという連載です。 私は、福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する出版社、株式会社労務研究所の代表取... -

2025年(令和7年)1月から労働者死傷病報告などの電子申請が義務化
じん肺法施行規則等の一部を改正する省令が令和6年3月18日に公布され、令和7年1月1日から施行されます。 この改正により、労働者死傷病報告や総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任報告など、労働安全衛生規則等に基づく特定の申請が... -

経営力強化支援事業補助金|新宿区の中小企業・個人事業主向け
2024年4月1日より新宿区内の事業者が、販売促進費や業務効率化のために取り組むITツールの導入等にかかる経費を補助してもらえる制度「経営力強化支援事業補助金」が始まりました。 IT・デジタル化のためにPOSレジを導入する場合や、製造設備の導入等には... -

2024年10月|社会保険適用拡大の対象企業がやるべきこと
現在、社会保険の適用範囲は段階的に拡大しており、2024年10月からは、従業員数51名以上の企業についても、社会保険の適用拡大の対象となります。該当する企業については、これまで社会保険非加入だった一部のパート・アルバイト従業員に対しても、社会保... -

健康経営の目的は?労務管理に活かす方法
従業員への健康管理を戦略的に実践する「健康経営」は、日本で広がりを見せて10年が経ちました。健康経営優良法人制度においては、上場企業のうち31%が健康経営度調査(2023年実施)に参加※しており、中〜大規模の企業においては健康経営の実践が当たり前... -

2025年「育児・介護休業法」大改正!人事必見、両立支援に役立つ福利厚生のポイント
2024年5月末に「改正育児・介護休業法」が公布されました。この大規模な改正に伴い、人事・総務担当者は労働環境の整備が求められています。 本記事は、「福利厚生をコストから投資へ」をビジョンに掲げる株式会社HQが、法改正のポイントや仕事と育児・介...